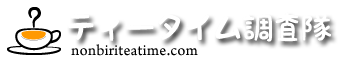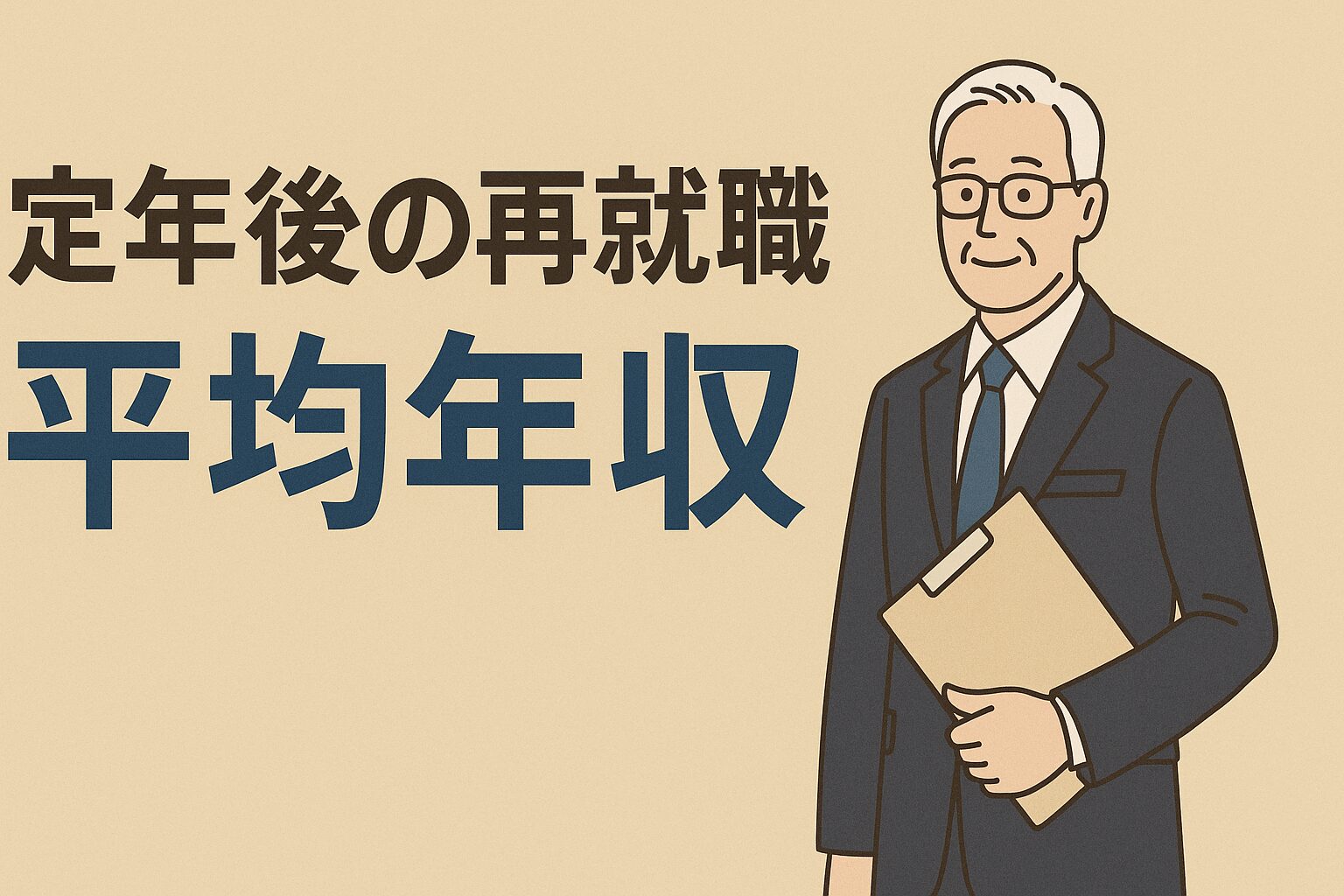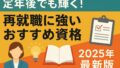定年を迎えた後も働き続ける人は年々増えています。しかし、再就職や再雇用では年収が大きく下がるのが現実です。
「一体どれくらい下がるの?」「どうすれば少しでも維持できるの?」と不安に感じる人も多いでしょう。
本記事では、最新の統計データをもとに、定年後の再就職における平均年収や年齢・性別・地域による違い、収入を減らさないための戦略を徹底解説します。
これからのライフプランを考える上で、ぜひ参考にしてください。
定年後再就職の平均年収データ
定年後に再就職した場合、年収はどれくらいになるのか――これは多くの人が気になるポイントです。この記事作成時点での国税庁「民間給与実態統計調査」と厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、60〜64歳の平均年収は約420〜440万円、65〜69歳では約340万円前後という結果が出ています。
定年前の水準と比べると、40%ほど下がるのが一般的です。特に再雇用制度を利用する場合は、給与が定年前の7割程度になるケースが多く、企業によっては半分以下になることもあります。
また、パーソル総合研究所の調査では、再雇用後の年収は平均44.3%減少しており、4人に1人は「半分以下になった」と回答しています。年収が下がる背景には、契約社員や嘱託社員といった非正規雇用への転換や、役職手当・残業代の減少があります。
一方で、職種によっては比較的高い年収を維持できる場合もあります。たとえば営業職は65歳以上でも約370万円、専門職や医療・法律分野では400万円を超えることもあります。つまり、再就職後の収入は職種・業種・地域によって差が大きいのです。
定年後の再就職を考える際は、「平均年収」だけを見るのではなく、自分が希望する職種や地域の相場を調べることが重要です。これにより、現実的な収入の見通しを立て、生活設計に反映させやすくなります。
年齢別(60〜64歳・65〜69歳)の収入傾向
年齢別に見ると、60〜64歳はまだ比較的高い年収を維持できる傾向があります。厚労省のデータでは、企業規模10人以上の場合、60〜64歳の平均年収は約423.9万円。これは定年前(55〜59歳)の約75%の水準です。一方、65〜69歳になると平均年収は約344.2万円に下がり、定年前の60%程度にまで減少します。
この年齢による差は、企業が高齢者雇用において体力や業務負担を考慮するため、業務内容を軽減する傾向があるからです。また、65歳を過ぎると年金の受給が始まる人も多く、企業側も給与より雇用の継続を重視する場合が増えます。
特に注意したいのは、65歳を境に雇用形態や勤務日数がさらに短縮されるケースです。フルタイム勤務から週3〜4日のパート勤務になると、年収は300万円を下回ることも珍しくありません。
そのため、65歳以降も安定した収入を得たい場合は、早めに転職やスキル取得を行い、定年後の働き方を設計しておく必要があります。
再雇用と再就職の違いによる年収差
定年後の働き方には大きく分けて「再雇用」と「再就職」の2つがあります。この違いは、年収にも直結します。
再雇用とは、同じ会社で定年後も働き続ける制度のことです。多くの場合、契約社員や嘱託社員として雇用され、仕事内容は定年前と似ていますが、給与は大幅に下がります。
国の調査では、再雇用後の給与は定年前の6〜8割程度が一般的で、管理職経験者でも役職手当がなくなるため、年収が半分近くになるケースもあります。再雇用は慣れた職場で働ける安心感がある反面、収入面では限界があるのが現実です。
一方、再就職は新しい会社に移ることを指します。この場合、経験やスキルによっては高い年収を提示されることもありますが、年齢の壁があるため、選択肢が限られることが多いです。
特に専門職や営業職、技術職であれば比較的高収入が狙えますが、事務職や軽作業などでは年収が200〜300万円台にとどまることも珍しくありません。
年収面で比較すると、再就職のほうが成功すれば再雇用より高収入になる可能性がありますが、失敗すれば逆に下がるリスクも高いのが特徴です。つまり、「安定を取るか、挑戦して収入アップを狙うか」という判断が必要になります。
定年を迎える前から、自分の希望や適性、ライフプランに合わせて、どちらの道を選ぶのかを決めておくことが大切です。
男女別の年収の特徴
定年後の年収には、男女間でも大きな差があります。国税庁の統計によると、60〜64歳男性の平均年収は約500万円弱ですが、女性は約250〜300万円と、ほぼ半分の水準です。
65〜69歳では男性が約380万円、女性は約200万円台前半となり、この差はほとんど縮まりません。
この背景には、現役時代の職種や働き方の違いがあります。男性は管理職やフルタイム勤務が多く、退職後もその経験を生かして比較的高収入の再就職先を見つけやすい傾向があります。
一方、女性はパートや非正規での勤務経験が多く、定年後も同様の雇用形態になることが多いため、平均年収が低くなります。
また、再就職時に選ぶ職種にも影響があります。男性は営業や技術系などの専門職が多いのに対し、女性は事務、販売、介護など体力や経験に合わせた職種を選びやすく、これが年収差に直結します。
とはいえ、介護や医療の資格を持つ女性は、60代でも年収300万円以上を確保できる場合があります。
このように、男女間の収入差は現役時代からの働き方の積み重ねによって生じており、定年後に突然解消されるものではありません。そのため、できれば50代のうちから資格取得やキャリアチェンジを検討することが、定年後の年収アップにつながります。
地域差による年収の違い
定年後の年収は、地域によっても大きく変わります。厚労省の統計では、都市部(特に東京・神奈川・愛知・大阪など)の60歳以上の平均月収は全国平均を大きく上回ります。
東京では60〜64歳の平均月収が約35万円、年収にすると420万円前後ですが、地方の一部では月収20万円台、年収300万円未満のケースも珍しくありません。
都市部が高収入になりやすい理由は、企業規模が大きく、専門職や管理職経験者を求める求人が多いことにあります。さらに、製造業やIT業、金融など、高付加価値な業種が集中している点も影響しています。
一方、地方では中小企業やサービス業が中心となり、時給制や短時間勤務の求人が多く、結果として年収が低くなります。
ただし、地方には生活費が安いという利点もあります。都市部で年収420万円、地方で年収300万円だとしても、家賃や物価を考慮すると、実質的な生活水準はほとんど変わらない場合もあります。
また、地方には地元ネットワークを生かして就業できるケースもあり、柔軟な働き方が可能です。
つまり、定年後に働く場所を選ぶ際は、単純な年収の数字だけでなく、生活コストや働きやすさも含めて判断することが重要です。
雇用契約形態の変化
定年後の年収が下がる大きな理由の一つは、雇用契約形態の変化です。定年前は正社員として働き、昇給や賞与、各種手当が支給されていた人でも、定年後は契約社員や嘱託社員、パートなどの非正規雇用になることが一般的です。これにより、基本給が減少するだけでなく、賞与がなくなったり、大幅に減額されたりします。
例えば、定年前に年収600万円だった人が、再雇用契約で基本給25万円、賞与なしとなれば、年収は約300万円にまで減ります。さらに、交通費の支給額が減少する場合や、残業代が発生しにくい勤務形態になることも多く、収入減に拍車がかかります。
この変化は法律や企業方針に基づくため、本人の努力だけでは避けられない部分もあります。ただし、転職活動を通じて正社員登用のある企業を探す、フリーランスや業務委託契約を活用するといった方法で、一定の年収水準を維持できる可能性はあります。
職務内容の変化と責任範囲の縮小
定年前は部署を統括する立場や、プロジェクトの責任者として働いていた人でも、定年後は現場作業や補助業務が中心になることが多いです。
これは、企業が高齢者雇用において体力面や健康面を考慮し、業務負担を軽くするための措置でもあります。
責任範囲が縮小されると、役職手当や責任手当がなくなり、給与も比例して下がります。また、業務の裁量権が小さくなることで、成果に基づくインセンティブや報奨金を得る機会も減少します。
ただし、専門的なスキルや資格を持つ人の場合は、責任範囲が狭くても高単価の仕事を請け負える場合があります。たとえば、技術コンサルタントや弁護士、医療関係の資格保持者などは、業務範囲が限定されても比較的高収入を維持しやすいです。
年功序列から成果主義への移行
かつての日本企業は年功序列が主流で、年齢や勤続年数に応じて給与が上がっていました。しかし近年は成果主義の導入が進み、特に定年後の雇用では「働いた分だけの報酬」という形が一般的です。
定年後の給与は、経験よりも現在の成果や生産性に基づいて決められることが多くなります。これは公平性の観点では合理的ですが、年齢による体力低下や新しい技術への適応速度の違いから、若手と同等の成果を出すことが難しい場合もあり、その結果、給与水準が下がるのです。
この影響を軽減するには、定年を迎える前から新しいスキルや知識を習得し、年齢に関係なく成果を出せる能力を高めておくことが重要です。
健康や体力面の影響
60歳を超えると、多くの人が体力や健康面で以前のような働き方を続けることが難しくなります。長時間勤務や重労働を避けるために勤務日数を減らしたり、パートタイム勤務に切り替えたりするケースが増えます。当然、その分給与も下がります。
また、健康上の理由で急な休職や入院が必要になることもあり、結果として安定した収入を維持することが難しくなります。このような健康面の影響は避けられない部分もありますが、日頃の生活習慣や運動習慣によってある程度は予防できます。
企業側の人件費抑制
最後に、企業が高齢者雇用で年収を抑えるのは、コスト面の理由も大きいです。定年後の社員に高額な給与を支払うと、若手社員の給与改善や新規採用に回す予算が減ってしまいます。そのため、多くの企業は定年後の給与水準を抑えつつ、雇用を確保する形を取ります。
ただし、即戦力性が高く、企業にとって利益貢献度の大きい人材には高額のオファーが出ることもあります。特に、人脈や専門知識を活かせる業界では、高齢者でも年収500万円以上を維持できる可能性があります。
スキルアップと資格取得
定年後も高い年収を維持するためには、スキルアップと資格取得が非常に有効です。特に需要の高い資格を持っていると、採用側からも「即戦力」として評価され、年収交渉がしやすくなります。
代表的な例としては、宅地建物取引士、社会保険労務士、簿記、介護福祉士、医療系資格、IT関連資格(MOS、ITパスポートなど)が挙げられます。
資格は単なる知識の証明ではなく、「この人は学び続ける姿勢がある」という評価にもつながります。また、資格取得を通して最新の知識やスキルを習得できるため、若手とも競える能力を維持できます。
特に50代後半から資格取得を始める人は増えており、定年前に資格を取っておけば、再就職市場で有利に働きます。たとえば介護職は60歳以上でも求人が多く、介護福祉士や実務者研修を持っていれば年収300〜350万円が狙えます。
高収入が期待できる職種の選び方
定年後の再就職で高収入を得るためには、職種選びが重要です。データによれば、営業職、専門職(医療・法律・コンサルタントなど)、ITエンジニア、技術職は比較的高収入を維持しやすい傾向があります。営業職は成果報酬型のため、年齢よりも実績や人脈が重視されます。
一方、事務職や軽作業は体力的には負担が少ないものの、年収は200〜300万円台にとどまることが多いです。高収入を目指すなら、自分の経験を活かせる専門性の高い職種を選び、求人数の多い都市部や成長産業に的を絞ると良いでしょう。
ネットワークと人脈の活用
定年後の再就職で意外と効果的なのが、人脈の活用です。現役時代の同僚や取引先、業界団体のつながりから再就職先を紹介してもらえるケースは少なくありません。こうした「縁故採用」は、求人票には出ない好条件の案件につながることも多いです。
また、LinkedInやビジネス交流会などを活用して、定年後も現役として活動していることをアピールすれば、新しい案件や副業の依頼が舞い込む可能性もあります。
副業・兼業の選択肢
定年後は、副業や兼業で収入を補うという選択肢も有効です。例えば、平日は契約社員として勤務し、週末は講師やコンサルタントとして働くことで、年収を底上げできます。副業の例としては、オンライン講師、ライティング、翻訳、動画編集、民泊運営などがあります。
副業の魅力は、時間や場所に縛られずに働けることです。特にオンライン系の副業は、体力面の負担も少なく、長期的に継続しやすいのが特徴です。
自営業やフリーランスへの転身
最後に、自営業やフリーランスとして独立するという選択肢もあります。長年培った専門知識や人脈を活かし、コンサルタント業や専門サービスを提供することで、高収入を狙える可能性があります。もちろんリスクも伴いますが、自由度の高い働き方を実現できます。
特に「定年後起業」は近年注目されており、小規模事業なら初期費用を抑えてスタートできるため、失敗リスクも比較的低く抑えられます。
営業職
営業職は定年後でも比較的高収入を維持できる職種のひとつです。成果報酬型が多く、年齢よりもこれまでの実績や人脈が評価されます。特に法人営業や高額商材(不動産・保険・BtoBサービスなど)を扱う仕事では、年収400万円以上を狙えるケースも珍しくありません。
また、営業職はコミュニケーション能力や信頼関係構築力が重要であり、経験豊富なシニア層は強みを発揮しやすい傾向にあります。再雇用よりも再就職、特に成果連動型の企業に入ることで、定年前と近い水準の収入を得られる可能性があります。
技術職(エンジニア系)
エンジニアや製造関連の技術職は、高齢者でも需要が高い職種です。特に製造業では熟練工や品質管理、設備保守などの経験者が重宝されます。IT分野でもシステム開発やインフラ管理のスキルがあれば、契約社員や業務委託で年収500万円以上を維持できることもあります。
ただし、新しい技術への対応力が求められるため、現役時代から継続的にスキルを更新しておくことが重要です。
事務・管理職
事務や管理職のポジションは、比較的体力負担が少なく長く働ける反面、年収水準はやや低めです。定年前に管理職経験があっても、再雇用や再就職では役職手当がなくなるため、年収300〜350万円程度になるケースが多いです。
ただし、財務、人事、総務など専門性の高い事務職では、経験を活かして400万円以上の年収が可能な場合もあります。
専門職(医療・法律・教育)
医師、看護師、弁護士、公認会計士、大学講師などの専門職は、定年後も高い年収を維持できる職種です。需要が安定しており、年齢よりも資格やスキルの有無が評価されます。
特に医療や介護分野は人手不足が深刻で、60歳を超えても年収500万円以上を稼ぐことが可能です。教育分野では、大学や専門学校の非常勤講師として長く活躍する人も多くいます。
サービス・販売業
サービス業や販売業は求人が多く、未経験でも始めやすい一方で、年収はやや低めです。フルタイム勤務でも年収250〜300万円程度が一般的で、パート勤務の場合はさらに低くなります。
しかし、接客スキルや外国語スキルがある場合、高級ホテルや観光業などで年収アップが可能な場合があります。観光立国を目指す日本では、インバウンド需要の高まりとともにこの分野でのシニア活躍の場が広がっています。
年金との組み合わせによる総収入
定年後は、再就職による給与と公的年金を組み合わせて生活するケースが多くなります。65歳以降に年金を受け取り始める人が多く、例えば年金年額200万円+再就職の年収340万円であれば、総収入は540万円程度になります。
ただし、年金は繰下げ受給や在職老齢年金制度の影響を受けるため、働きながら年金を受給する場合は減額されることがあります。
特に60〜64歳の在職老齢年金は、賃金+年金額が一定基準を超えると支給停止になる仕組みです。そのため、働き方や収入見込みを踏まえて、最も有利な受給タイミングを検討する必要があります。
生活費の見直し術
収入が減る定年後は、生活費の見直しが不可欠です。まず固定費から削減すると効果的で、具体的には通信費の格安プランへの切り替え、保険の見直し、車の維持費削減などが挙げられます。
また、食費は外食を減らし自炊中心にすることで大幅に節約可能です。光熱費は、省エネ家電やLED照明の導入、契約アンペア数の見直しで削減できます。これらを合わせると、年間数十万円の節約も可能です。
税金・社会保険料の負担軽減策
定年後も働く場合、税金や社会保険料が意外と大きな負担になります。年収が大きく下がっても、前年所得に基づく住民税や国民健康保険料はすぐには減らないため、初年度は特に注意が必要です。
節税方法としては、扶養控除や医療費控除の活用、小規模企業共済やiDeCoへの加入などがあります。また、収入が一定以下の場合、国民健康保険料や介護保険料が軽減される制度もあるため、市区町村の窓口で確認しておくと良いでしょう。
貯蓄の活用と投資の工夫
定年後は収入減を補うために、貯蓄や投資を活用することも視野に入れるべきです。ただし、生活費をすべて投資に回すのはリスクが高いため、生活防衛資金(最低2年分)を確保した上で運用を行うのが鉄則です。
安全性を重視するなら個人向け国債や定期預金、少しリスクを取るならインデックスファンドや高配当株などが選択肢になります。投資は収入の補助的役割として捉えるのが賢明です。
セカンドライフのための資金計画
定年後の生活を安定させるには、60代以降のライフプランを見据えた資金計画が欠かせません。ポイントは「収入+年金+資産運用」の三本柱で考えることです。
また、健康維持や趣味、旅行なども含めた支出計画を立て、無理のない範囲で余暇を楽しむことが大切です。計画を立てておけば、不安を減らし、セカンドライフをより充実したものにできます。
まとめ
定年後の再就職では、年収は定年前に比べて平均4割前後下がるのが一般的です。60〜64歳で約420〜440万円、65〜69歳で約340万円前後が目安ですが、職種や地域、雇用形態によって差は大きくなります。
収入減をカバーするためには、資格取得やスキルアップ、人脈活用、副業などの戦略が有効です。また、年金や生活費の見直し、税金対策、資産運用を組み合わせることで、安定したセカンドライフを実現できます。
「収入を減らさないための準備」と「減った後の生活設計」、この二つを定年前から進めておくことが、充実した定年後のカギとなります。